TECH BEAT Shizuoka 2024 AFTER BURNER#3 開催レポート

7月に開催した「TECH BEAT Shizuoka 2024」で芽生えたイノベーションへの意識をさらに深め、具体的なビジネスの可能性を追求する「TECH BEAT Shizuoka 2024 AFTER BURNER」。第3回目は、浜松いわた信用金庫が運営するイノベーション拠点「FUSE」と連携し、資生堂、日本テレビで新規事業開発・外部連携を推進するお2人と、浜松で挑戦を続けるアトツギ経営者のお2人をゲストにお迎えしてトークセッションを実施しました。シリコンバレーのエコシステムを参考に企業家やスタートアップが集い、刺激し合う場を目指して設置された「FUSE」には、県西部地域の企業や自治体から約50名の参加者が集まりました。



第一部 CES 2025に見るイノベーションの起こし方
登壇者
- 資生堂グローバルイノベーションセンター ブランド価値開発研究所 グループマネージャー 中西 裕子 氏
- 日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局 R&D ラボ部次長 加藤 友規 氏
- モデレーター/株式会社 HEART CATCH 代表取締役、TECH BEAT Shizuoka プロデューサー 西村 真里子 氏
- モデレーター/Carbide Ventures General Partner、TECH BEAT Shizuoka プロデューサー 堀内 健后 氏
第一部では、米・ロサンゼルスで開催される世界最大級のテクノロジー展示会「CES」に参加したことのある登壇者陣からCES2025の注目テーマや出展内容を紹介いただきながら、CESをイノベーション促進にどのように活用していけば良いかを考えました。
資生堂は靴に取り付けた小型センサーと解析アプリを用いて歩様の美しさを評価し、一人ひとりの状態に合わせた歩き方や顔の印象などについて提案を行う「歩容美測定」、カメラを使って肌内外の毛細血管の状態を測定し、肌状態の傾向を予測し最適な美容アドバイスを提供する「Beauty Alive Circulation Check(ビューティー・アライブ・サーキュレーション・チェック)」で「CESイノベーションアワード2025」を受賞。中西氏からは、資生堂グローバルイノベーションセンターが進めているオープンイノベーションプロジェクトの経過発表の場としてCESを活用しており、製品化前に試作品や技術に対するフィードバックを得ることができる点が大きな魅力であると教えていただきました。
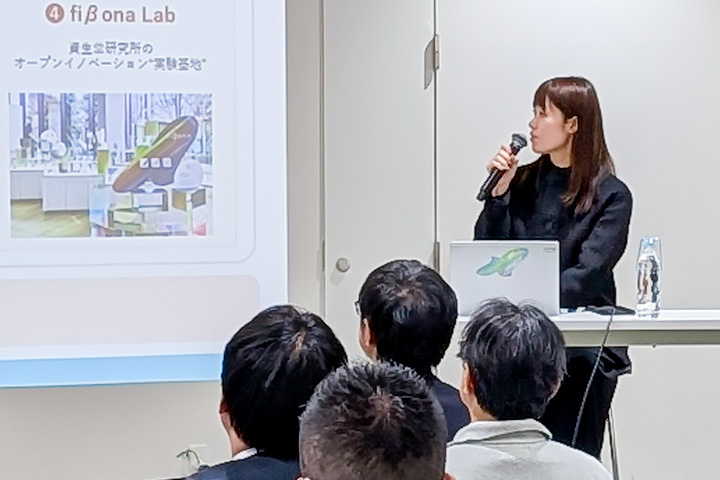
続いて日本テレビホールディングスの加藤氏からは、同社が実施する街ナカ・家ナカのエンタメ体験や未来社会・未来世代への貢献をテーマに、3Dデータの取得が可能なスタジオで録画したアーティストの動画を用いたミュージックビデオ制作コンテストの実施や、宇宙からの生中継など、既存の放送事業の枠組みを超えて次世代のエンターテインメント創出を目指す取組について紹介いただきました。
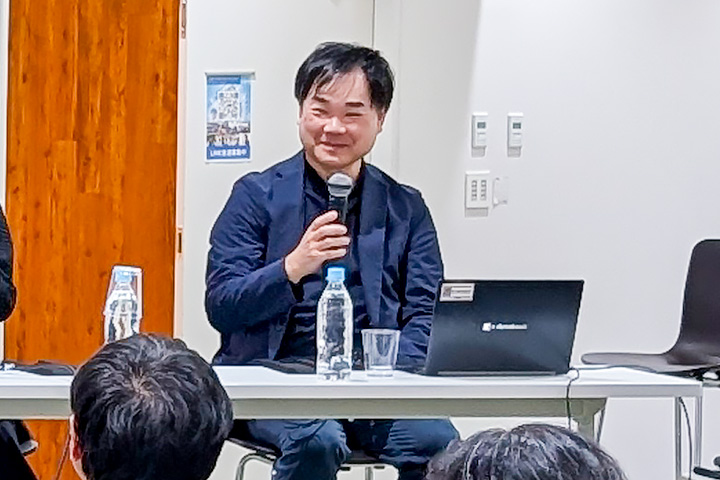
CES2025に現地参加した登壇者の皆さんが注目したのが「AIの製品・サービスへの実装」と「エイジ・ヘルステック」。様々な分野で製品へのAI実装が進み、一人ひとりに合ったサービス提供が当たり前になる時代が間近に迫っていることを実感したそうです。また、エイジテック分野では、世界に先駆けて高齢社会に突入する日本企業の良い製品やサービスが沢山あるにも関わらず同分野への日本企業の出展が少なかった、という指摘もありました。
CESには様々な国・地域から人が集まるため、多様な価値観から製品やサービスへのフィードバックが得られることも大きな魅力です。登壇者からは日本では当たり前・見向きもされない製品やサービスが世界で高く評価される可能性があること、「日本の普通」を「世界の普通」と考えず、世界を目指して製品やサービスを展開することも選択肢の1つであることなどを、参加者に対して熱く語っていただきました。
第二部 地元・浜松企業の新規事業への挑戦とその悩み
登壇者
- 株式会社鳥善 代表取締役 伊達 善隆 氏
- 鳥居食品株式会社 代表取締役 鳥居 大資 氏
- 資生堂グローバルイノベーションセンター ブランド価値開発研究所 グループマネージャー 中西 裕子 氏
- 日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局 R&D ラボ部次長 加藤 友規 氏
- モデレーター/株式会社 HEART CATCH 代表取締役、TECH BEAT Shizuoka プロデューサー 西村 真里子 氏
- モデレーター/Carbide Ventures General Partner、TECH BEAT Shizuoka プロデューサー 堀内 健后 氏
第二部では、地元浜松で事業を展開する2社から新規事業の取組を紹介いただきました。浜松の老舗飲食企業である鳥善は、「街食堂」プロジェクトを通じて地域の様々な企業や人を繋ぐ取組を行っています。浜松市内の交流拠点「街食堂」で毎週水曜日に開催される勉強・交流会「水曜日のヨル喫茶」で出会ったスズキの社員の方から「インド人社員の口に合う食事を日本で探すのが大変」という話を聞いた伊達社長は、日本に住むインド人が安心して食べられるベジタリアン対応・本場の味に近い食事キットの開発に着手しました。この取組はスズキを始め、インド人エンジニアを雇用する大企業のほか、健康意識が高い消費者からも注目を集めています。

また、浜松で100年以上ソース製造を手掛ける鳥居食品は、消費者に食卓での新しいソースの活用方法を提案するため、2025年夏、自社工場のそばに和食・洋食など幅広い料理と自社のソースを組み合わせたメニューを提供する「トリイソース食堂」を開業する計画です。鳥居社長からは、この取組を通じてソースの可能性を広げ、日本の食文化と併せて海外のソース市場を開拓していく、という戦略を共有いただきました。

各企業の取組からは、商品の開発製造に携わる社員が様々な属性の人々との交流を通じて商品・技術に対する反応を直接感じることが、新規事業開発を進めるうえで大切である、という第一部との共通点が浮き彫りになりました。また、地域の高齢者を食堂のスタッフとして起用する案や、健康志向の人々にも人気が高いヴィーガン・ベジタリアン向けの食品開発など、地域や自社の課題として取り組んでいることがCESのエイジ・ヘルステックという世界のテーマにつながっていることに気づかされる、非常に濃い内容のセッションとなりました。

セッション終盤、堀内氏から、「地元企業の挑戦を誰が・どのような形で支援していくべきか。地元企業を地域全体が応援するような仕組みを作り、新規事業開発を進めるうえで乗り越えなければいけない資金確保や人的ネットワークの形成を支援する仕組みを今後、考えていく必要があるのではないか。」という問題提起がありました。今回実施した「AFTER BURNER #3」の内容を踏まえて、「地域の企業の挑戦を後押しするためにTECH BEAT Shizuokaは何ができるか?」を改めて考え、これからも皆様に様々な人々との交流や学びの機会を提供していきたいと思います!


